車のタイヤ交換は、簡単!タイヤ交換は、皆さんどこで交換されてますか?寒い時期や春先の暖かくなった時期にスタッドレスから夏タイヤ、またその逆もあるかと思います。タイヤ交換は、ディーラーや車の修理工場、カー専門店、ガソリンスタンドなどでタイヤ交換します。しかしタイヤ交換は自分でも出来る簡単な作業です!今回は、タイヤ交換を自分でも出来るタイヤ交換をご紹介します。
タイヤの交換時期
スタッドレスタイヤ、夏タイヤの交換は、いつ?
タイヤは、どのタイミングで交換すればいいのでしょうか?スタッドレスタイヤの交換を雪が降る日の前日に変えたり、最悪なケースでは降ってしまってから交換する人も…。
雪が降ってからでは交換してくれる工場やお店に持っていかれないです!
持って行かれたとしても混雑していることも。
では、交換時期はいつがいいのでしょうか。
季節によるタイヤ交換
タイヤ交換を行うタイミング。日本の四季でいう晩秋、初春の時期に合わせて行います。
タイヤの交換時期を日本の季節を交えながら解説します😄
スタッドレスタイヤの交換はいつ?
暦のうえから考えると交換の時期は、晩秋の時期。
11月末までにタイヤの交換が望ましいと考えられます。
もっと早めの交換も必要な地域もあるかもしれませんが… 一般的には、この時期の交換をおすすめします。
12月に入ると突然の雪も降ることもあるので注意が必要!
旧暦での晩秋:
旧暦は、太陽太陰暦で9月が晩秋とされます。
※ 例)2019年の旧暦晩秋:9月29日(9月後半)から10月27日(10月後半)太陰暦での月の満ち欠けにより毎年、時期が変化します。
二十四節季の晩秋:
二十飲節季の晩秋は、寒霧から立冬前日の霧降が期間となります。
※ 例)2019年の二十四節季の晩秋は、10月8日から11月7日になります。

夏タイヤの交換はいつ?
夏タイヤは、春先に交換!
夏タイヤの交換する時期は、一般的に春の季節で2月下旬から3月末ごろがいいタイミングになるかと。
暦の上での春と秋はいつなのでしょう?
旧暦での春先
旧暦では、1月から3月で新暦では、2月から4月くらいになります。
二十四節季の春
立春から立夏の前日まで(2019年は、2月4日から5月5日)
話しは、少しずれましたが、参考程度に覚えておくのもいいのではなかろうかと😄
ざっくりとした説明になりましたが、結論からすると!
スタッドレスは11月末~12月初めに交換
夏タイヤは、2月末~3月末に交換がおすすめ。
タイヤの摩耗による交換時期
タイヤの交換の原因の一つでもある摩耗について。
タイヤは、路面との摩擦によって走行を可能にしている。
このことからタイヤの接地面は摩耗をします。
タイヤ摩耗のサイン
タイヤ摩耗のサインはショルダーの▲印に対して横方向にラインが見えていきます。このようにラインが出てくるのは交換のサインです。
乗り続けていると、スリップの原因になり非常に危険な状態です。交換が必要となります!

<タイヤの摩耗サイン>
タイヤ溝の基準
タイヤ溝が1.6mm未満は、車検は受からない。
新品のタイヤの溝は、8mmほどあります。タイヤの摩耗が進み残り1.6mmまでが最小限界寸です。
以上の基準値よりも前に交換をおすすめします。
32,000Kmが交換の目安!
一般的なタイヤのゴムの摩耗は、走行距離が約5,000Kmにつき1mm減るとされている。
タイヤ溝を知るには、溝を計測できる専用治具があります。
ガソリンスタンドなどで…
ガソリンスタンドで「タイヤ交換が必要ですね」と言われたことありませんか?本当に交換しないといけないのでしょうか?
不安だけが残ります!
こんな時にあると便利なのが、タイヤ溝ゲージ。
ダッシュボードに入れておくことで、自分で測って確認できます!
タイヤ溝を測ることで交換が必要なのかどうなのかの判断が自分で決められます。
また交換が必要ならばその交換時期も考えることができます。
ご自身の目で確かめて交換の時期を考えては、いかがでしょうか!
走行距離とタイヤの摩耗:
一般的なタイヤのゴムの摩耗は約5,000Kmで1mmが減るといわれてますが、新品のタイヤ溝はメーカーやサイズにもよりますが、約8mmぐらいになっています。
タイヤの摩耗は、路面状況や使用状況にもよりますが、上の摩耗距離で考えると約32,000Kmの走行距離でタイヤ溝は1.6mmなる。
交換の目安は、走行距離で考えると約32,000Kmです。
年数だと、年間10,000Kmの走行として約3年に1回の交換も必要と考えられます。
※上記の交換時期の目安は、計算上になります。走行状況や使用状況、環境によって違いがでます。
タイヤの摩耗がひどい場合、雨の日の走行は、路面のグリップ力が落ち滑りやすくなっています。
横断歩道やマンホール!滑ると感じたらタイヤ交換をしておきましょう。


車のタイヤ交換
タイヤは、路面に接地し回転しています。自動車の中で重要なパーツの一つにもなっており、もっとも安全性が必要とされています。
タイヤは重要なパーツなので、組付けの際は、充分に気を付けて作業を行いましょう!
※ケガのないように手袋を着け、安全に作業をしましょう!
タイヤ交換に必要な工具
タイヤを外す工具を用意。
- ホイールレンチ
- トルクレンチ
- ジャッキスタンド
- ジャッキ
- 輪留め
- 軍手、グローブ(作業用手袋)
上記が必要となる道具です。
ホイールナットをゆるめる
インパクトレンチを使わずにホイールレンチを使った方法をご紹介!
サイドブレーキやフットブレーキ、Pレンジに入れ車体が動かないようにします。

<フットブレーキ>
今回、タイヤ交換をするお車は、「三菱トッポさん」になります。
軽自動車のトッポさんは、ホイールナット4穴です😄
4穴ならナット4個、5穴は5個です。
ホイールナットを外す
4輪のタイヤの全てのホイールナットをゆるめる。
ホイールレンチを用意しホイールナットを少しゆるめます。
車体は、ジャッキアップせずにそのままの状態でゆるめます。
ナットは完全にゆるめない(仮ゆるめ)、外さない!
ホイールナットは少しゆるめるだけです!完全にゆるめないように!またホイールレンチをつま先で押し下げないようにしましょう。
左回り(反時計回り)に回すとゆるむ。
(ちなみに右方向(時計廻り)に回すと締める方向です)
ホイールナットのゆるめ方
ホイールナットをゆるめ方は、ホイールレンチに足裏(かかと)を乗せ下に向かって体重をかけ一気にゆるめる。
ホイールレンチは、必ず下に向かって押し下げるようにする。
下記の写真のように足をかけて押し下げる。

<ホイールナットをゆるめる(仮)>
ホイールレンチの先端が地面にあたって止まればいいのですが、ホイールレンチが短かったりホイールナットの位置が上にある場合は、回転し脛(すね)にあたりケガをすることもあります。
よろしくない作業!

昔、整備士の頃に教わりました!このような作業でケガがありました。
ジャッキアップを先に行うとホイールナットに力が入らずにうまく外せないこともあるので先に緩めておきます。
ナットは、きつく締めこまれているので腕の力だけではうまく緩められないので足裏を使って緩めます。
タイヤの輪止め
ジャッキアップをする。この時の注意点は、前輪を上げるなら後輪側のタイヤの前後に輪止めを行います。
後ろからジャッキアップするならば前輪のタイヤの前後に輪止めで車体が動かないようにします。

<輪止め>
車体が動かないようにしっかりと固定する。
車体を上げる
所定の位置(ジャッキポイント)にガレージジャッキやパンタジャッキをかける。ジャッキポイントにスタンドをかけ車体を浮かせます。
ジャッキをかけるところ:
デフやロアアーム、ジャッキポイント
ガレージジャッキはこちらがおすすめです!

<ジャッキアップポイント>
車体のドア下側、上記の写真⇧の位置にジャッキスタンドを設置して車体を支えます。
場所は、ドアの下の方にあります。
ジャッキスタンドを設置した際に、交換するタイヤ、車輪を車体の下に置きます。車体が落ちた時、安全のためです。くれぐれも転倒のないように!
車が上がったらフットブレーキやサイドブレーキ、Pレンジを解除します。
タイヤを外す
車体はジャッキスタンドで支えられて浮いている状態。

<タイヤを浮かせる>
ホイールナットは、ゆるまっているので簡単に外せます。

<ホイールナット>
ホイールナットにホイールレンチを押し当てながら緩めます。
同時にタイヤを右回転させると速く外せますよ。締める時は、この逆です。

<ホイールナットを外す>
タイヤを外す時はタイヤの左右を両ひざで固定すると安定して外せます。
安全面も良くなります!この要領で4本のタイヤを外していきます😄

<タイヤを固定>
※一部外車で緩み防止のため、左右逆になっていることもあります!
電動インパクトレンチの使い方
電動インパクトレンチでホイールナットを外す方法。
一般的には、ホイールレンチを使いホイールナットを外しますが、便利で簡単に外すことができる電動のインパクトレンチを解説します。
車体をジャッキアップしジャッキポイントにスタンドをかけ地面から浮かせる。
ジャッキアップの際の手順と注意点「ホイールナットを緩める(ホイールレンチ)」もう一度振り返ってみます。
前輪を浮かせ後輪に輪止めを行います。また後輪を上げる時は、前輪の前後に輪止めを置き車体が動かないようにします。
ジャッキスタンドをかける時は、柔らかな地面などジャッキスタンドが沈みこまないところでの作業を行います。
ジャッキポイントにジャッキスタンドを設置し作業を行いましょう。
ジャッキスタンドをかけたら次は、タイヤを外します。
ホイールナットをゆるめる時は、タイヤの左右を両ひざを使って固定し動かない様にします。

<両ひざで固定>
タイヤを外す時の地上からの高さ
タイヤは、地面から約3㎝~5㎝ほどの高さで浮かせます。
高すぎると腰を痛めたり、タイヤが落下した場合にケガの原因にもなります。
次に電動インパクトを使いホイールナットを外します。回転方向を確認しゆるめます。
外したタイヤは、車体の下に少しもぐらせて置きます。
ジャッキが外れた時の車体へのダメージを減らす緩衝の役割をします。
タイヤ交換の作業は、スタッドレス/夏タイヤ共に同じ方法で行います。

電動インパクトレンチのデメリットは⁈
そうです。電動のインパクトレンチの音は、めっちゃうるさいです!
ご近所さんに迷惑にならないように使いましょう!
タイヤを装着
タイヤの装着。夏タイヤ⇔スタッドレスタイヤのです。
AT車の場合は、レンジのロック解除ボタンでPレンジの解除を行います。
MT車は、ニュートラルにしておきます。
タイヤを取り付ける
タイヤを取り付ける。
ハブボルトを回転させながらハブボルトの1本を頂点(上)で止めます。
ホイールのボルト穴をのぞきながら頂点(上)になったハブボルトを見つけます。
見つけたハブボルトを穴と合わせ穴に通し残り3本をボルト穴に通していきます。

<ハブボルトを通す>
タイヤを外した時と同じように、両ひざで押さえてホイールナットを取り付けます。

<両ひざでタイヤを支える>
初めに両手でホイールナット2本を締めていきます(仮締め)。
両手がむずかったら片手で1本ずつ締めていきます。
手で締められるところまでしめる。

<ホイールナットをしめる>
ホイールレンチをホイールナットにはめ込み、右に回しタイヤを左回転させながらしめていきます。
ホイールナットとハブボルトのセンターを必ず確認ししめていきましょう。
センターが出ていないと、走行中にホイールナットがガタつき緩んでいきます。最悪の場合、タイヤが外れ大事故になります!
必ずセンターに合わせてしめていきましょう。
ホイールナットをしめる
ホイールナットを目一杯しめる。
ホイールレンチを使ってさらにしめます。
ホイールナットを対角線にしめていきます。
先ずは、(写真の)左からしめて

<ホイールレンチでしめる>
次に右をしめてます。

<ホイールナットを順番にしめる>
続いて上をしめる。

<右側をしめる>
最後は、下側のホイールナットをしめて仮締めが終ります!

<上側をしめる>
ホイールナットをしめる時は、レンチを手の平でたたいてしめていきます。
手のひらが痛かったらやめておきましょう!
トルクレンチの使い方
トルクレンチを使って規定のトルクでタイヤをしめる。
ジャッキを使い車を降ろします。この時、ジャッキスタンドも外す。
Pレンジやフットブレーキ、サイドブレーキを効かせて車を動かない状態にする。
MT車の場合は、ギアを入れておきます。

<トルクレンチ>
トルクレンジを使う!
トルクレンチの持ち手の端につまみがあるので規格のトルクに設定!
※メーカーによって違う場合もあるのでよく確認が必要。
軽自動車: 80~105N・m (8~10.5㎏)
普通乗用車: 90~120N・m (9~12㎏)
「三菱 トッポさん」は、軽自動車なので90N・mで締めていきます。
本締めも対角線状でしめる。

<トルクレンジで本締め>
※レンチが滑らないように気を付けましょう!

上に位置するホイールナットをしっかりと本締めします。

次に右側のホイールナットをしめる。

対角線上にナットをしめ完了です。残りのタイヤも同じ方法で本締めを行います。
タイヤの表記やサイズなどを知っておくことで選ぶ時に便利で困らないです!合わせておすすめします。



タイヤ交換の動画
タイヤ交換に必要な工具や使い方を説明しています!こちらも合わせておすすめです!
タイヤの購入はどこで
タイヤ交換、購入はどこで?
皆さんは、タイヤが摩耗したりスタッドレスが必要な時どうされてますか。
カー用品店、タイヤ専門店などで購入しておられるかと。
タイヤ選びにお店以外の選び方があります!
それはネットを使った選び方
最近は、ネットをお使いになられる方もかなり増えてきています。
自宅でゆっくり選べられ、お出かけするガソリン代、時間を節約することができます!
それではネットでのサービスはどのような物なのか見ていきましょう!
ネットで申し込むと近くのガソリンスタンドにタイヤが運送され交換の予約も入りタイヤの持ち運びもいらなくてガソリンスタンドで交換もしてくれるサービスです!
ガソリンスタンドだと待ち時間は、コーヒーでも飲みながら待つことができ、楽ですね!
さらに!こちらも
自分でタイヤ交換をしたい人にもネットを使うのもあり!
タイヤのバランスもやってもらえて自宅に届けてもらえて便利です!
タイヤ選びにはいくつもの選択肢がありますが、ネットを試してみては、いかがでしょうか。
まとめ
今回は、冬の前や春先のタイヤ交換の方法や交換のタイミング時期をご紹介しました。
スタッドレスタイヤや夏タイヤの交換には、ホイールレンチ、電動インパクトで脱着をしていきました。
その時に、両ひざでタイヤを固定したり、ホイールレンチとタイヤを回すことで早く緩めたり締めたりもできました。
注意点もありましたね。ホイールとハブボルトのセンターを合わせることはとても重要でした。
交換のタイミングを考え自分で交換、DIYにチャレンジしてください!
今回は、ここまでとなります。ご覧になられていかがだったでしょうか。また、別の記事もご覧下さい。
mamecoroエンジンは、動画もやっておりますので、そちらの方もご視聴、チャンネル登録も宜しくお願いします。
ご覧いただけたらうれしいです。
皆様の愛車がいつまでも綺麗であり続け安全かつ事故の無いことを祈っております。
では、また次回お会いしましょう!
.jpg)


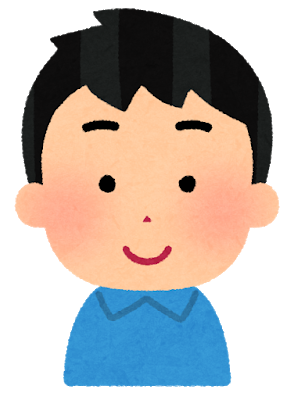










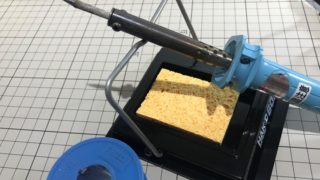





-320x180.jpg)



